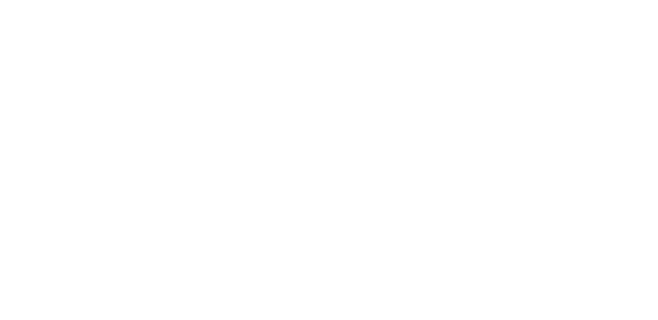真嘉比あるき終了
2020年2月12日 Category: 沖縄ある記 Comment : 0
2020年2月11日(火・祝日)、「真嘉比あるき」を実施しました。
RBCから取材の申し込みがあったのでドキドキしましたが(笑)、何とか格好はついたかなと自画自賛。
あるきは思っていた展開と「若干違ったかな」でしたが、まあそれはそれでイイでしょう。
真嘉比の前区長・玉城さん、花城さんの話が聞けたので、たいへん助かりましたね。
ありがとうございました。

天気も温度も、歩くにはちょうどイイ感じ。
快適でした。

RBCの6時代のニュースで紹介されました。
こっちからは何もしなかったのに丁寧に作ってもらって、ありがたいですね。

今度の日曜・16日には「石嶺あるき」をやりますので、よろしくです。
みなさん、来てね~!
<三嶋>

「石嶺あるき」のお誘い
2020年2月6日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comment : 0
怒涛の春が、いつものようにやって来ています。
今回は、「石嶺あるき」の告知です。
前回あげた「真嘉比あるき」もまだ終わってませんが、忘れていた(笑)ので、緊急告知となりました。
呆れた人も少なくないでしょうが(許して)、懲りずに応援よろしくです。
日時は2020年2月16日(日)、午前10時~12時。

したがって2月の3週は、11日が真嘉比、16日が石嶺あるきとなりますね。
いまさらながらですが、忙しくてすみませんね。
重ねてよろしくお願いします。
<三嶋>

第3回「真嘉比あるき」を行います
2020年1月20日 Category: 沖縄ある記, 案内 Comments : 2
お久しぶりです。
まだ何とか続いてますよ。
今回は、第3回「真嘉比あるき」告知です。
昨年に引き続くので、「またか」と思う人もいるかもしれませんが、そんなことは気にせずお付き合いいただければ、みんなハッピーだわ(笑)。
2020年2月11日(火曜祝日)、午前10時~12時です。

昨年からいろいろ忙しく、こちらもサボってしまいました。
一回サボるとクセになるんですよね。
ごめんなさい。
これからは、また頑張っていきますので、よろしくです(ほんとか?)
<三嶋>

消えゆく旧東恩納博物館
2019年3月30日 Category: Myある記 Comment : 0
琉米歴史研究会の喜舎場静夫さんと、久しぶりに帰沖された川平朝清さん(91歳)を迎え、うるま市石川の旧東恩納博物館を訪れた。
県立博物館の出発点となった場所だが、最近、取り壊しが決まったことから、同館で通訳を勤めていた川平さんに喜舎場さんが知らせ、最後の「別れ」をセッティングしたもの。同時に、次世代にも伝えたいと、沖縄尚学高校や広島・大阪の高校生に向けたワークショップも行われたので、有意義なひと時に立ち会わせていただいた。

中央・川平朝清さん、右端・喜舎場静夫さん

旧東恩納博物館を訪れた高校生たち
旧東恩納博物館は、1945(昭和20)年8月、米国海軍政府のワトキンス政治部長・ハンナ教育部長らにより、石川市東恩納に沖縄陳列館として設立された。
戦前は大学教授だったハンナ少佐(博士)らは、琉球文化の素晴らしさに敬意を払い、戦火で失われたその復興を願うと、首里城や円覚寺の焼け跡を自らまわり、数々の美術工芸品等を拾い集めてその保存と陳列を図ったほか、芸能復興や教科書編さんなどにも努めた。
ハンナ少佐はわずか1年ほどの滞在だったのだが、打ちひしがれていたウチナーンチュが勇気と誇りを取り戻すことを願い、寄り添うための努力を惜しまなかった。破壊と殺戮ばかりではなく、そんな心ある米軍人もいたのである。
現在の県立博物館に収蔵されている戦前の品々の多くは、この沖縄陳列館(東恩納博物館)由来なのだが、その原点ともいうべき場所が、今、失われようとしている。


1946(昭和21)年ごろの東恩納博物館(上)とその庭(下)
<写真:琉米歴史研究会>


現在の建物と瓦礫に埋まった庭
朝鮮戦争を契機として戦後復興を成し遂げた日本社会は、高度成長期を経て、今もなお(すでに破綻しているという声をよそに)米国を中心とする「強欲資本主義」を追認している。
「本土並み」の平和と暮らしを希求した沖縄も、本土と同化するかたちで経済成長路線をひた走ってきたのであるが、その陰で、沖縄らしい自然や文化、芸術を重視して来た人たちの声は、疎んじられて来た。ウチナーンチュの魂や誇りをそこに見出し、次世代に残す責務があるという指摘はかき消されて来たのである。
その意味でも、東恩納博物館の功績は讃えられてしかるべきだろう。
しかし、那覇新都心の中心部にできた、新しい県立博物館・美術館のにぎわういとは対照的に、原点ともいうべきこの場所は、収蔵品が首里の博物館に移動して以来、役割を終えた場所として放置されてきた。
個人所有であったことがその理由と思われるが、沖縄の戦後史を語る公的な建造物として位置付け、何らかの形で保存・活用することはできなかったのか。
その責を行政に求めるのは容易いのだが、市民・県民の後押しが足りなかったのも事実だ。自分もふくめた県民一人ひとりに、地域の歴史・文化に対する自覚が不足していた、と反省するのである。
足元にある先人の遺産をないがしろにして、地域の未来を築くことはできない。
関係者をふくめて、一人ひとりがこの建物と場所を失うことになった事実を、重く受け止める必要があると思うのである。
<三嶋>

真嘉比の写真展終了
2019年3月26日 Category: 沖縄ある記, 活動クリップ Comment : 0
去った3月24日日曜、「地域写真展in真嘉比」が無事終了。
諸般の事情で、たった1日だけの展示会となったのが残念。地域の方々にも申し訳なかく、反省させられたが、次回の課題ということで勘弁願いたい。

地域で行う写真展は、毎回ディープな話で盛り上がる。
とくに、区画整理を経て一気に街並みが変わった真嘉比では、住んでいた家や馴染みの店、近所づきあいのあった人の話題などで、お喋りはつきない。

若い時分は必死で働き、子育てに追われてきた人たちが、当時を懐かしむ年代になって、しばし思い出に浸っている。誰もがそれぞれの悩みや悲しみを抱きながら、泣きつ笑いつそれなりの人生を生きて来たのだ。
写真に刻まれた、今はなき家並みや通りの中に、つかの間、自分だけの思い出を見つけてもらえたのなら、嬉しい限りである。
<三嶋>