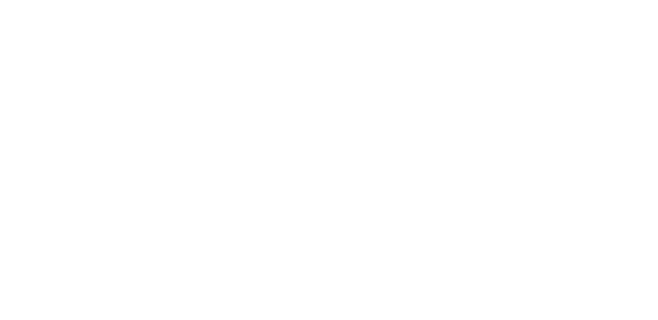琉米文化会館のサービス
2012年7月23日 Category: Myある記 Comment : 0

1951(昭和26)年から復帰前まで、那覇にあった琉米文化会館の閉館時間は、夜9時半だった。
誰もが日々の暮らしに追われていた時代、実生活をしばし忘れ、読書や文化・芸術に癒されたいと望んだ人は多かっただろうし、明るい未来を夢見て勉強に打ち込んだ学生も多かっただろう。そんな人には、夜遅くまで開いている同館の存在は、とてもありがたかったはずだ。
敗戦からわずか6年後に開館したそこは図書館であり、ギャラリーであり、人々が集える総合文化センターであった。米軍の住民統治の装置だという話がささやかれたが、かつて働いていた大嶺昇さんによれば、地域の人々へのサービスを第一に考え、住民のために汗を流すことをいとわずスタッフは働いていたという。
琉米文化会館の話を思い出したのは、あちこちの図書館で最近、自動貸出しを目にする機会が増えたからである。
コスト削減がその理由だろうが、経済効率優先の考えを持ち込む発想には、人間を相手にしているという自覚が欠如しているように思えてならない。読書の楽しさや集積された知の体系に誘う図書館の役割は、利用者との触れ合いが基本であり、貸し出し業務は、そのきっかけだと考えるからである。
経費削減のおり、「忙しいし人がいない」という答えが聞こえてきそうであるが、宮古・八重山の県立図書館分館廃止などを断行した先に、どんな未来があるというのか。予算・人員が確保できれば・・・といわれても、縮小経済が続くなかそれは望めないだろう。
だとすればどうするのか。行政と住民との共生が残された道ではないか。
もはや行政がすべて賄うことはできないからこそ、行政批判をくり返してきた住民もふくめて、地域のことは地域で解決するための仕組みを構築するのである。みんなで応分の汗をかくことをモットーに、コストをかけない地域の交流拠点として、図書館や文化施設を使い倒すのである。
焼け跡から文化復興を成し遂げた人たちに習い、ボクらも行動する時を迎えているのではないだろうか。
(三嶋)
※写真は昭和30年代の那覇琉米文化会館。提供は大嶺昇さん